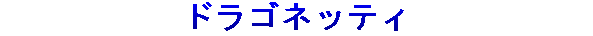
チェロ、コントラバスが先導するフーガを書いた。」
という伝説で知られるコントラバスの名手ドメニコ・ドラゴネッティ。
彼の楽器が3弦であったことは残っている写真からも明らかです。
彼の調弦については諸説あり、4度調弦の上からGDAだったとも5度調弦のADG
であったともいわれています。
古くフランスでは3弦、5度調弦が主流だったという説もありますが、
「そもそも調弦が定まっていなかった」というのが間違いないでしょう。
奏者によって、また同じ奏者でも曲によって調弦を変えていたらしいのです。
イタリア人ドラゴネッティはどんな調弦をしていたのでしょう?
彼の代表作コントラバス協奏曲(イ長調)におけるハーモニクスの使い方を見ると
やはり4度調弦なのではないかと思われるのですが、
一番最後の音の記譜上のGは3弦4度調弦では出すことができない音なのです。
私の手もとにある楽譜を基にすると第3弦がG以下である必要があります。
(ちなみに先述のベートーヴェンのトリオのメロディーも一番下はGです。)
さらにハーモニクス技法を考えると第1弦もGでなければなりません。
Dの開放を多用することから第2弦はDだと考えて良いでしょう。
これらのことから導き出された仮説は、ドラゴネッティの調弦は
GDG、またはソロ調弦をしてAEAの4度5度の混合であったと考えられます。
以上に述べたことはE.Nanny氏が校訂した楽譜をもとにした「仮説」です。
校訂の際にNanny氏が4度調弦に合わせて手を加えている可能性がありますので
この仮説に確信を持つことはできません。
いつの日か手稿譜または原点版を見てみたいものです。
だとすれば上記の仮説は全く的外れですのでご注意下さい。
